善光寺坂 紹介動画 作りました!
■「善光寺坂」 名の由来
坂の途中に朱色門の美しい善光寺があります。こちらの寺の名をとって坂名としたとされています。
善光寺は 慶長7年(1602)の創建と伝えられ、
伝通院(徳川将軍家の菩提寺)の塔頭で、縁受院と称しました。
当時、近くに伝通院の裏門があったと言われています。
その後、明治17年(1884)に善光寺と改称し、信州の善光寺の分院と なったそう。
寺は古いですが、「善光寺」「善光寺坂」としては明治時代の新しい名前なんですね。
■慈眼院(じげんいん)澤蔵司稲荷
伝通院の学寮に、澤蔵司(たくぞうす)という修行僧がいました。
わずか三年で 浄土宗の奥義を極めたといわれています。
元和六年(1620)五月七日の夜、学寮長の極山和尚(ごくざんおしょう)の夢枕に立ちました。
「そもそも 余は千代田城の内の稲荷大明神(いなりだいみょうじん)である。
かねて浄土宗の勉学をしたいと思っていたが、多年の希望をここに達した。
今より元の神にかえるが、永く当山(伝通院)を守護して、恩に報いよう。」
と告げて、暁(あかつき)の雲にかくれたという話が紹介されています。
(『江戸名所図会(ずえ)』『江戸志』
そこで、伝通院の住職・「廓山上人(かくざんしょうにん)は、
澤蔵司稲荷を境内に祭り、慈眼院を別当寺(べっとうじ)としました。
江戸時代から参詣する人が多く繁栄したそう。
『東京名所図会』には、「東裏の崖下に狐棲(こせい)、(狐のすむ)の洞穴あり」とあります。
今も霊窟(おあな)と称する窪地があり、奥に洞穴があって、稲荷が祭られています。
伝通院の門前のそば屋に、沢蔵司はよくそばを食べに行ったんだあとか。
沢蔵司が来たときは、売り上げの中に必ず木の葉が入っていたと伝えられ、
主人は、沢蔵司は稲荷大明神であったのかと驚き、毎朝「お初(はつ)」のそばを供え、
いなりそばと称したのだと言います。
沢蔵司は、てんぷらそばがお気に入り (古川柳(こせんりゅう))
■むくの木
善光寺坂の途中に「椋(むく)」の木があります。
目通り4.7m 樹高8m余 推定樹齢300年だとか。
60年前の東京大空襲で被災し、樹幹の2/3を焼失し樹皮は傷んでおり、
最近は内側が空洞状況になりつつあるとの事。
もともとは、沢蔵司(たくぞうす)御神木としてムクノキを植えたとされていましたが
時代が経って、 道路の真ん中になり、邪魔だからと何度も伐採が行われようとしたが、
不慮の事故が続き「これは澤蔵司の祟りだ」と、
伐採はとりやめになったという話が紹介 されています。
善光寺坂へのアクセスは
→丸ノ内線・南北線 「後楽園」 徒歩7分
三田線・大江戸線 「春日」 徒歩5分
お部屋探しはオレンジルームへ
◆ 東京都内のお部屋探しはこちら
http://www.orangeroom.jp/
◆ 文京区内のお部屋探しはこちら
http://bunkyo-life.jp/
◆ 神楽坂周辺のお部屋探しはこちら
http://kagurazaka-area.jp/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
プロパティエージェント株式会社
オレンジルーム
東京都文京区小石川 1-14-3
THE TOWER KOISHIKAWA 1階
フリーダイヤル 0120-974-002
E-MAIL info@orangeroom.jp
URL : http://www.orangeroom.jp
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
コメント
この動画へのコメント
この動画の評価
orangeroomさんのプロフィール
 |
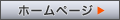 |
ブログに貼る
PeeVee.TVおすすめ
orangeroomさんの他の動画











